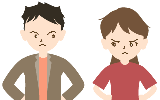当事者間の問題(手切れ金・慰謝料肩代わり)
当事者間の慰謝料
|
|
不倫というのは、自由意思で成り立つ関係ですので、一方が独身だと偽って関係を持っていたとか一方的なレイプなどの特別な場合を除いては、原則として、当事者間において慰謝料は生じません。 ただし、相手が未成年で社会経験に乏しく、異性関係も無かったという場合においては、当事者間においても慰謝料請求を認める判例があります。 |
| 昭和44年9月26日 最高裁判所 判決 |
要旨 「女性が、情交関係を結んだ当時男性に妻のあることを知っていたとしても、その一事によって、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求が、民法708条の法の精神に反して当然に許されないものと画一的に解すべきではない。 女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を勘酌し、右情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求は許容されるべきであり、このように解しても民法708条に示された法の精神に反するものではないというべきである。」 |
|---|
手切れ金

|
一般に、別れ話になった場合、「手切れ金」名目で金銭の支払いが生じることがありますが、法的な支払義務があるものではありません。 |
手切れ金は、任意に双方が合意するのであれば、取り決めをすることも自由ですが、その要求について、「支払わないと(家族や勤務先に)ばらす」などと脅迫したような場合には、強迫による意思表示の取り消し(民法96条1項)によって返還請求することが可能であるとともに、脅迫罪(刑法第222条)や恐喝罪(刑法第249条)で刑事処罰を求め得る余地もあります。
不倫当事者間の婚約(離婚が成立したら結婚するという約束)は、法的保護に値する利益である「平穏な夫婦関係の破壊」を前提としているため、原則として、公序良俗に反し無効です。
よって、「騙された」「約束を破られた」等という主張は、残念ながら、法的には通用しません。
そもそも離婚というものは、原則として、夫婦のいずれか一方の意思のみで成立させることは出来ませんし、有責配偶者からの離婚請求は特段の事情がない限り認められませんので、「原始的不能」でもあります。
慰謝料の肩代わり(履行引受)

|
例えば、夫に不倫された妻が、夫の不倫相手に慰謝料請求をした場合に、不倫した夫が、その愛人の代わりに慰謝料を肩代わりして支払う、または、その愛人に手渡すという場合があります。 |
| 債務引受 | ⇒ | 債務者が債権者に対して履行すべき義務を、引受者が引き受けるという内容 「債権者」と「引受者」との間の契約 |
| 履行引受 | ⇒ | 債務者が債権者に対して履行すべき義務を、引受者が行う、または補てんするという内容 「債務者」と「引受者」との間の契約 |
この場合の「履行引受」契約というのは、共同不法行為者間で慰謝料の負担割合を定める内容の契約となりますので、原則として、法的に有効です。