内縁・婚約の不倫
内縁とは
|
|
内縁とは、婚姻の意思を持って夫婦共同生活を営み、社会的にも夫婦と認められているにもかかわらず、婚姻の届出をしていないために法律上は夫婦として認められない事実上の夫婦関係と定義されています。 当初の判例においては、将来において適法な婚姻をなすことを目的とする「婚姻の予約」であり、この予約の不当な破棄に対しては債務不履行責任が成立するという解釈がなされており、「婚約破棄」の一種として構成されていました。 その後、内縁関係は、婚姻に準じる準婚関係であり、内縁の不当破棄は離婚に準じる不法行為責任を生じうるという法理が採用されるに至りました。 |
| 昭和33年4月11日 最高裁判所 判決 |
要旨 いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異るものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。 内縁も保護せられるべき生活関係に外ならないのであるから、内縁が正当の理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができるのである。 されば、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を求めることもできるものといわなければならない。 |
|---|
内縁の要件
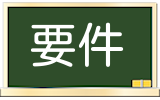
|
法的に認められる「内縁」の要件としては、以下の3つが必要となります。
|
実質的に夫婦と同様であるという実体がなければ、同居期間が長期に及んでいても、単なる「同棲」であり、「内縁」とはなりません。
経済的援助をしながら性的関係を維持する「妾関係」や、夫婦共同生活の実態がなく単に密かに情を通じ合っているだけの「私通関係」も「内縁」とは区別されます。
内縁の類型
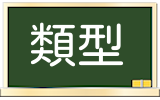
|
内縁が成立するのは、原則として、以下の3種類の類型になります。
|
当事者において婚姻適齢の要件を満たさない場合にも内縁関係は成立します(大判大8・4・23)。
当事者において再婚禁止期間の要件を満たさない場合にも内縁関係は成立します(大判昭6・11・27)。
婚約とは
|
|
婚約というのは、「結婚の予約」という契約の一種であるため、婚約者が他の異性と肉体関係を持った場合、その婚約者に慰謝料請求が出来るのは当然として、その浮気相手に対しても、一定の場合、慰謝料請求をすることが可能です。 もっとも、この場合、その相手が責任を負うのは、あくまで、婚約者がいるということを認識していた上で、不貞行為に至った場合に限られます。 独身男女間においては、「自由恋愛」が原則であるため、単に交際相手がいるという認識だけだった場合には、不法行為責任は負いません。 |
| 昭和38年9月5日 最高裁判所 判決 |
要旨 当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約し長期にわたり肉体関係を継続するなど原審判決認定の事情(原審判決理由参照)のもとにおいて、一方の当事者が正当の理由がなくこれを破棄したときは、たとえ当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、世上の習慣に従つて結納をかわし、もしくは同棲していなくても、相手方は、慰藉料の請求をすることができる。 |
|---|
婚約当事者の不貞行為に関する相手方の責任について、その浮気相手である第三者も不法行為責任を負うと判示されております。
| 昭和53年10月5日 大阪高等裁判所 判決 |
要旨 被控訴人は、元婚約者と共同して控訴人が婚約に基づいて得た、誠実に交際をした後婚姻し、終生夫婦として共同生活をすることを期待すべき地位を違法に侵害したものであるから、控訴人に対し不法行為による損害賠償義務を免れないというべきである。 |
|---|
婚約の要件
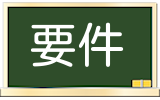
|
法的に認められる「婚約」の要件としては、以下の3つが必要となります。
|
婚約には、必ずしも結納その他の儀式は不要とされています。
ただし、結婚を前提とした交際であるととともに、具体的な結婚準備を進めていた、または結婚を前提とする生活基盤が形成されていたことが重要になります。
また、婚約者の浮気相手に慰謝料請求をする場合には、少なくとも、その浮気相手が、婚約の事実を知っていた上で自由意思で肉体関係を結んでいたことまでが要件として必要となります。




